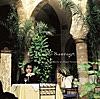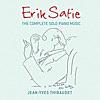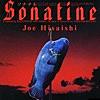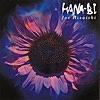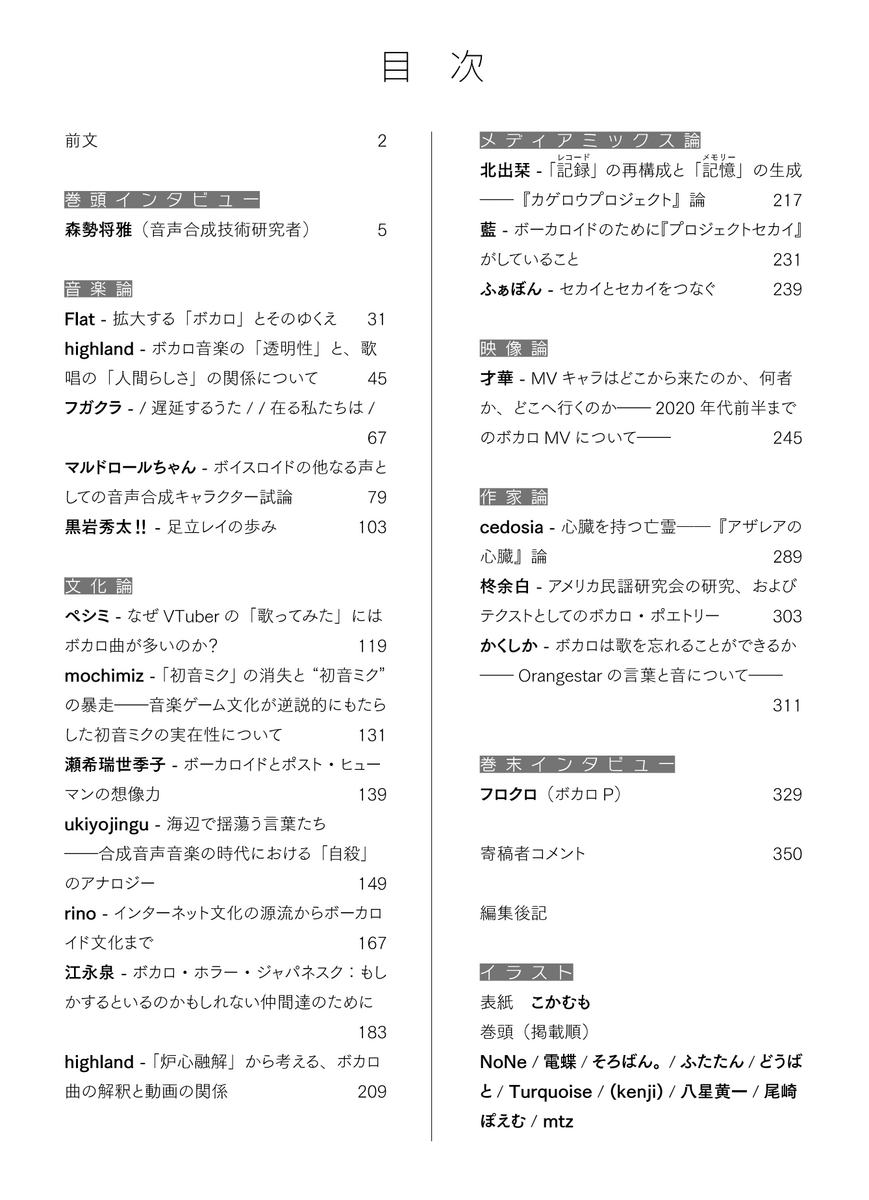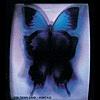昨日出した音楽寄稿文について、早速第一弾として大間無題さんの寄稿文をお送りします。主題はタイトルの通り音楽アニメ『リズと青い鳥』を<物語>シリーズ的に読み解くという非常に物珍しい論考になっています。寄稿文の大凡の基準として読んでいただければと思います。それでは本編へどうぞ(rino)
・本編
この映画『リズと青い鳥』(二〇一八年)が一見して簡単にその全容を理解できるような単純明快な作品でないことは、恐らく誰もが一見して簡単に理解できる、単純明快な事実にあたるだろう。かといって、単に複雑と言うことも、簡単に難解と言うことも、それはそれで作品の印象を捉え損ねているように思う。この映画にカルトじみたようなところはまったくなく、むしろ普遍的な魅力というものを備えていることもまた、大なり小なり、誰もに理解されるはずだ。説明不足なのにわかりやすいというか、わかりやすいようで不可解というか、総じて曖昧で捉えどころのない、不思議な作品であるように思う。
端的に言って、いかにも考察を誘う作品だ。
そんな訳で、この『リズと青い鳥』を<物語>シリーズとともに読む」は、すでにインターネットに数多ある『リズと青い鳥』における論考の末席を汚すべく書かれたものである。既出の考察やインタビューなどにはざっと目を通し、可能な限り妥当性の高い読解を目指した――が、あくまでもそれは個人の見解を超えるものではなく、妥当性が高くとも妥当と呼べるような代物ではないことを、初めにここで断っておきたい。当たり前のことかもしれないが、こればっかりは努力とか筆力とかで超えられる壁ではない。なんとなれば、<物語>シリーズとともに読む理由からして、なににつけても西尾維新を参照しなければなにも考えることができないという、個人的な悪癖によるものでしかなく、『リズと青い鳥』と<物語>シリーズとを対応させる必然性を、その内容から根拠立てて説明できるわけではないのだから。必然性に客観性がない。それこそ、徹頭徹尾、個人の見解である。
長々と言い訳じみた前置きをしてきたが、要は与太の類として、肩の力を抜いて読んでほしいということだ。シリアスで痛切、エモーショナルで感傷的な作品を論じたものでこそあるが、この文章自体はシリアスでも痛切でもなければ、エモーショナルでも感傷的でもない。ここまでの文章で、思考のチャンネルを『リズと青い鳥』から<物語>シリーズに、馬鹿な掛け合いで満ちた楽しげな小説に切り替えていただければ幸いである。
いい加減に本題に入るとしよう。とにかく言及し甲斐のあるフックに満ち満ちた映画ではあるが、ここではあえて、クライマックスのシーンを最初に取り上げたい。この作品の山場はなんといっても、みぞれが手加減をやめ、希美との実力の差が明らかになる場面だろう。「切ない真実に、あなたは涙するー」というキャッチコピーが公式サイトに掲げられているように、物語はこのシーンに辿り着くべく進行していると言っても過言ではないはずだ。
しかしながら、このシーンはインパクトがあるわりに理解しにくい、飲み込みにくいものがあるように思う。問題の「切ない真実」というのは、「みぞれが希美のために実力を隠していたこと」だろう。しかし、最初に見たときに引っかかったのは、その「真実」を隠していたのはみぞれであり、それに「涙する」のは希美の方であるという点だ。
恐らくここで違和感を覚えた観客は多いのではないだろうか。事実、公式サイトで見れる座談会トークなるものでは「Q:はじめてご覧になったとき、みぞれと希美、どちらの目線で見られましたか?」という質問に、序盤に関してはインタビュイーの全員がみぞれの名前を挙げている。少なくとも前半においては、この映画が描いてきたのは他の誰も知らないみぞれの気持ちであり、観客はみぞれしか知らないことを知っている以上、みぞれの一人称視点から映画を見ることになるのが自然だろう。このストーリーは希美が離れ離れになる『リズと青い鳥』に自分たちを重ねるシーンを始めとして、一貫してみぞれが感じる別離の予感を軸として展開していく。みぞれが予感している別れならば、それはみぞれに対して降りかかるものであり、観客はみぞれから希美が去っていくような結末を予想するはずだ。ところが事実はその逆で、肝心要の「真実」とやらを観客が知るのは希美と同じタイミングである。
このことは普通に考えればおかしい。みぞれだけが感じている不安が描写されるならば、みぞれだけが知っている実力もまた描写されていたほうが然るべきだし、どんでん返しが売り文句の三文ドラマでもないのだから、観客が前もってそのことを知っていたとしても、そのことで物語が不成立になるようなことはないからだ。しかし、ラストに至るまで、みぞれの秘密が明かされることはない。このような描写の取捨選択によって、みぞれが語り手として自身のすべてを詳らかにしているはずだと暗に信頼していた観客は、突如として彼女の視点から弾き出されてしまう。このみぞれから希美への視点の移動は、件のシーンの映像が涙で滲んだようにぼやけだすことにも表れているだろう。最終的に「涙する」ことになる「あなた」は希美の方なのだ。ここで感じられるのは、「私はさっきまでみぞれだったのに、いつの間にか希美になっていた」というような奇妙な状況である。
よって、この映画から信頼できない語り手の叙述トリックを感じるのは恐らく間違いではない。みぞれの実力を描写し、それを発揮するみぞれの決意を描写し、クライマックスを最後まで飛び立つ青い鳥の視点から描くこともできたはずだ。そうした一切は、最終的に観客の視点をひっくり返すために、恣意的に隠されていたと見るべきだろう。この映画の端々から感じる描写の面での不親切さ(例えばラストの理科室のシーンでは「みぞれに頑張って、とか言って……」という希美の台詞があるが、そうした描写は口パクで「頑張ろう」と言ったシーンしかない。とはいえ、これは間を置いて2回やっているので、ちゃんと刷り込んでおこうという気遣いも感じられるが)は、叙述トリックを極端に不自然に見せないための、木を隠すための森としての機能も持っているように思える。
では、そのようなギミックが仕込まれていたのはなぜなのだろうか。つまり、観客がそのようにしてみぞれに、言ってしまえば裏切られることは、(もちろん叙述トリック自体の持つ飛び道具的な脅かしは除くとして)どのような効果を生んでいるだろう。それは、語り手であるはずのみぞれの秘密を知らなかった観客の立場を、親友であるはずのみぞれの秘密を知らなかったという希美の立場と同調させるという点にあるように思う。ここで描写されているのは単なる2人の実力差だけでなく、みぞれが希美のためにそれを隠してきたという2人の関係の非対称を知ってしまった希美の寄る辺なさである。言い換えれば、このシーンは希美と一緒に驚いてもらうことを、希美と同じショックを観客に与えることを目的に作られているはずなのだ。
恐らく、作中作としての『リズと青い鳥』の効果もこの点に関わっている。みぞれの演奏の直前のシーンでは、2人がこの童話に重ねる自分たちの立場を逆転させたことが描かれているが、このことは先に確認した視点の移動と組み合わせることができるだろう。希美が青い鳥を見送るリズの立場に置かれることと、視点がみぞれから希美に移ることによって、観客だけはずっとリズの立場からストーリーを観ることになるのだ。クライマックスのシーンは、童話の『リズと青い鳥』に表れているような「別れの予感に葛藤する主人公が、最後にはその別離を受け入れる」といういかにも童話らしい基本的なカタルシスのツイストとして読むことができるだろう。「別れの予感に葛藤する」みぞれと「最後には別離を受け入れる」希美が別人であるということ、そしてその2つの視点を縫い合わせることによって、童話と同じひとつのドラマを形成すること。これが映画『リズと青い鳥』で描かれている内容のもっとも基本的な理解であるように思う。
このように整理すると、第三楽章のタイトルにもなっている「愛ゆえの決断」という言葉がかなり微妙な位置にあることがわかるだろう。作中でも言われているように、ここでの決断とはリズが青い鳥を空に帰すという決断である。麗奈の言葉を借りて作中の現実に当てはめるならば、その内容はみぞれの「本気の音が聴きたい」と願う希美の決断となるだろう。ところが、実際に希美がそうした決断をした描写はなく、むしろそのことにいたく衝撃を受けている様子が描かれている。「あなたが青い鳥だったら?」という新山先生の言葉を受けたみぞれは、「希美の決めたことが私の決めたこと」という自らの思いに照らして、「リズの選択を、青い鳥は止められない。だって青い鳥は、リズのことが大好きだから。悲しくても、飛び立つしかない」というが、繰り返すように希美とみぞれとの間に実際に『リズと青い鳥』と同じようなやり取りがあったわけではないのだ。この希美の「愛ゆえの決断」は、いわばみぞれが解釈したものとして存在していると言うことができるだろう。麗奈はみぞれに対して「希美先輩が自分に合わせてくれると思ってない」と言ったが、先の台詞はそうした不信を克服した結果として発されたのだと考えられる。配役の交換という面から見るならば、みぞれは「愛ゆえの決断」を想定することで、リズの役を希美に移したとも言えるだろう。
整理するならば、ジョハリの窓よろしく、希美自身から見た希美とみぞれから見た希美による、二種類の「決断」を考える必要があるということになる。そこで、まずは希美の視点での「愛ゆえの決断」について考えてみたい。その内容を、本文では「本気の音が聴きたい」とまとめたが、では、希美がどの時点でかような決断をしたのかを探ってみる。さきにも「頑張ろう」という台詞に少し触れたが、希美のそうした意思が最初に表れたのはどこだったか。
しかしこの考え方はどこかおかしい。そもそもの話、希美の性格を鑑みれば、逆に「自分に合わせて実力をセーブして欲しい」なんてことを思っていたタイミングが作中に一瞬だってあったはずがないことは自明だからだ。「本番、楽しみだね」という希美の台詞があるが、その意図は優子が宣言した「今年の目標はコンクールで金を取ることです(中略)みんなで支えあって、最強の北宇治を作っていこう」という目標と対応するものだろう。もちろん、相手の内心を斟酌して手加減をするような「支えあい」が求められているわけではない。であれば、表れたもなにも、「愛ゆえの決断」はそうした部活動への愛着の一環として、ずっとそこに存在していたと考えることが自然なはずだ。反対に、みぞれの手加減はこうした部の目標に対する連帯意識の希薄さの表れであると考えることもできるだろう。
つまり時系列としては、『新山先生の言葉によって「みぞれから見た希美」の決断が先に行われ、「希美自身」の決断がそれに従った』ではなく、『「希美自身」の決断ははじめから為されていて、紆余曲折を経た後に、新山先生とのやり取りによって「みぞれから見た希美」の決断が追いついた』ということになるはずなのだ。『リズと青い鳥』とはいわば、希美のメッセージがみぞれに正しい意味で届くまでの物語であると言ってもいいかもしれない。
逆算になってしまうが、ストーリーの内容をこのようにまとめることで、序盤のある描写を伏線として解釈することができる。希美が『リズと青い鳥』の童話を語って聞かせるシーンだ。
「ねえ、きみ。きみ、名前なんていうの?」
「私、傘木希美。一緒に吹部入らない?」
ここで用いられているギミックは、1つ目の鉤括弧で括った台詞が、2つ目の台詞によって、過去に実際に希美が口にした台詞の回想であることが明らかになるということである。このような、後になってから文脈を取り替えることで遡及的に発言の意味する内容を宙吊りにするような描写は、希美とみぞれとの間のすれ違いにまつわる物語とその結末の伏線とも捉えられるだろう。もっとも、このような解釈は自己言及的に解釈の可能性を擁護するところがあるので、わりと詭弁じみているような感もあるが。
しかし、物語の流れをこのように要約すると、肝心のみぞれの演奏に希美が受ける衝撃を位置づけられなくなってしまう。はじめから「愛ゆえの決断」が存在したとすれば、その実現にショックを受けることと矛盾を来すようになるのは言うに及ばすというものだろう。このことを解決するためには、希美の決断の範囲をさらに厳密に考える必要がある。希美の発したメッセージとみぞれに受け取られたメッセージとの間に違いがあれば、その落差こそ、希美のショックの正体となるだろう。物語をミスコミュニケーションの解消としてではなく、ミスコミュニケーションの変化として解釈しようというわけだ。希美が「頑張ろう」というのは、具体的になにをどうして欲しかったのか。みぞれはそこからなにを読み取り、なにを読み取れなかったのか。
改めて言うまでもないかもしれないが、これはみぞれが実力を隠していたこと、逆に言えば希美がみぞれの実力を知らなかったことに関わっている。みぞれと希美の実力差を踏まえれば、みぞれが希美に合わせて手を抜くか、希美がみぞれの演奏を「支える」、いわば踏み台としての役割を負うかの二択しかない。もちろん、そのどちらも「頑張ろう」という台詞で想定された内容ではないだろうー前提の実力差を踏まえていないのだから。つまり、みぞれの「本気の音が聴きたい」としてまとめた希美の意思は、「本気」の範囲として、自身のそれを大きく上回るものをそもそも想定していないのである。
こうした実力の定義を巡るエピソードとして、本編1期の一幕を見ることもできるだろう。この問題は滝先生がオーディションに対する反対意見を退けるにあたって言った「三年生が一年生より上手ければ良いだけのことです。もっとも、一年生より下手だけど大会には出たいというような上級生がいるなら、別ですが」という発言にわかりやすく表現されているように思う。ここで用いられているレトリックは重要だ。この言い分に反論が起こらなかったということは、「一年生より下手だけど大会には出たいというような上級生」はいなかったということになる。しかし、この発言がでるまで反対していた部員は実際にいたのだ。つまり、その反対意見の内容を書き出すならば、「一年生より下手だけど大会には出たい。ただし、仮にも全国を目指している以上、そんなことは言えないので大会に出るからにはあえて実力をはっきりさせることはせず、一年生よりは上手いという体面を保ったまま出させて欲しい」となるだろう。仮に自分が満足する結果になったとしても、それはあくまで集団の利益に適ったものであり、その結果たまたま私の気分が良くなったところでそんなものは単なる副産物に過ぎない、これは私欲を排した無私の願いである――という体面が必要なのだ。作中時点の去年まで、年功序列という明らかに非合理かつ非合目的的な規則が採用されていたのは、ひとえにそうした建前として使いやすいからだろう。その意味では優れて合理かつ合目的的と言い直すべきかも知れない。
繰り返すが、「一年生より下手だけど大会には出たい」と主張するような部員はひとりだっていない。そんなことをしては体面が崩れてしまうからだ。そう思うならば、主張する内容は「実際に演奏が上手い」という大義名分、大会に出るに値するという証拠の方である。例えば優子は「演奏技術なんてなくても香織先輩は素敵なのでどうかソロを吹かせてあげてください」なんてことは言わない。オーディションの不正を疑い、香織先輩の実力が反映されていないと主張するのだ。これはいわば滝先生が年功序列が「上手ければ良い」という大義名分を反故にし、実力で劣る上級生を保護するものであるということを暴き立てたように、優子もまた、このオーディションは大義名分に反すると主張している訳だ。これを単にあらぬ疑いとして片付けることは不可能だろう。ここであくまで滝先生の判断が正しいと信じろというのは、年功序列に当てはめるならば無条件に上級生の方が上手いということを信じろというのと同じ理屈になってしまう。だからこそ、別の評価基準として多数決を用いた再オーディションが必要となったのだ。
そして、希美が「頑張ろう」というときに要求していたものは、まさに「一年生より下手だけど大会には出たい。ただし、仮にも全国を目指している以上、そんなことは言えないので大会に出るからにはあえて実力をはっきりさせることはせず、一年生よりは上手いという体を保ったまま出させて欲しい」に相当しないだろうか。希美はオーディションでみぞれと同じパートを争うような立場でこそないが、「みぞれに負けたくなくて」というように、練習へのモチベーションの多くをみぞれと「同等になる」という部分に置いていることがわかる。そして「本番、楽しみだね」という台詞と前後する形で「希美は、練習が好き?」「好きだよ。めっちゃ好き」というやり取りがあることから、みぞれと「同等」であるということが、本番に対して重要な意味を持つという点で、オーディションと対応していると考えることができるだろう。そして、どちらの場合でも八百長は許されないーそういった「支えあい」が求められていないことは、先に確認した通りである。つまり、彼女がみぞれに求めていたのは手加減でもなければ全力でもなく、「全力という体で手加減する」ことだと考えられる。もちろん、みぞれの実力を知らない本人にそんなつもりはなく、文字通りの「本気の音」を望んでいたつもりなのだろうが、彼女がこの台詞を口にするごとにー いや、口にしてはいないが。それは無言のうちにある、まさに言外の意図なのだから ー優子が麗奈に対して行ったような取引を、みぞれに迫っていることになるのである。
こうした言外の意図は、香織の場合にも見て取ることができるー優子が目にした、「ソロオーディション/絶対吹く」という書き込みだ。優子の行動や麗奈の葛藤は、このメッセージに従ったものとしても解釈できる。あくまでオーディションの結果を受け入れようとする香織だが、同時に明日香に対しては「言ってほしくない。冗談でも、高坂さんがいいとか」というように、建前を、つまり大義名分を抜きにすれば、なにがなんでも麗奈の実力を認めたくなかったことだろう。「一年生より下手だけどソロは吹きたい」と、そう思っていたことだろう。
そして香織の場合も希美の場合も、建前の裏の私的な欲望とでもいうべきものが、実際に公的な状況で実現してしまえば、必ずや罪悪感を背負うことになるはずだ。こうしたアンビバレンスを考えるにあたっては、『化物語』(二〇〇六年)の「するがモンキー」のエピソードを寓話として取り上げるのがわかりやすいと思う。香織がオーディションに勝ちたいと願った時、それを叶えようとした優子は、いわばレイニーデビルと同じ位置にいないだろうか。一見すると、この一連の事態の責任は優子にあるように思えるし、また優子自身もあくまで自分でその責任を取るつもりでいるようだが、このように捉えると解釈は変わってくるだろう。忍野メメが「被害者面が気に食わねえっつってんだよ」というように、優子のようなわかりやすいわがままではなく、麗奈が「やりにくい」というような、香織の無垢な善性の方にこそ、事態の原因は求められるべきなのだ。
例えば、もしも仮に優子の要求通りに麗奈が手加減をして、その結果、香織がソロを勝ち取ったなら、そのとき香織に責任がないと言えるだろうか。いや、ミステリでもないのだから*1クイボノに則って考える必要もないし、この場合はあくまで優子の責任であると言えるかもしれないが、そもそも問題の本質は麗奈が「いま私が勝ったら悪者になる」というような状況の方である。優子というキャラクターはその状況がひとりの人間に象徴されたものとしても捉えられるだろう。優子が麗奈に頭を下げるときの、「いじめられたって言っていい」という台詞は、すでにそうした状況が出来上がっていることが念頭になければ読むことができない――「優子先輩に脅されました」と言って、信じてもらえるだけの状況が元から存在するのでなければ、こんな取引は成立しないだろう。ならば、優子という個人は描かれず、代わりに不特定多数の圧力のようなものが描写されていたとしたらどうだろう。その結果として麗奈が折れてしまい、香織がオーディションに勝ったなら、そのときも香織に責任はないのだろうか。
臥煙伊豆湖の「誤解を解く努力をしないというのは、嘘をついているのと同じなんだよ」という台詞は、こうした状況を想定すれば正しく読み解くことができるだろう。認めているが認めきれない、諦めているが諦めきれない、というような両義的なメッセージは、まさに認めていてること、諦めていることによって、逆説的にも最大限の「認めたくない」「諦めたくない」という意思表示として受け取られてしまう。香織の書き込みを目にした優子はもちろんのこと、「もう、いい。戦場ヶ原先輩のことも、もういい」「もう、いいから。諦めるから」という神原駿河に「そんな泣きそうな顔でー何が諦められる」と返す阿良々木暦を思い浮かべることでも、このジレンマは実感として理解できることだろう。顔 ーまさに言外の意図である。臥煙伊豆湖も忍野メメも、単なる言葉を越えた次元で、本当に認めるのでなければ認めたことにはならないということを言っているのだろう。重し蟹や迷い牛にも共通する「願いを叶える」という要素から、怪異の性質を「わかっているけれど、それでも……」といった内心を斟酌する存在として解釈するならば、専門家の言葉としての一貫性を感じられる台詞である。
このように、それ自体は単なる純粋な願いとしてあるものが、周囲による解釈を経ることによって罪悪感を伴う、罪深いものに変化してしまうという構図は、『リズと青い鳥』にも見ることができる――というか、『響け! ユーフォニアム』(二〇一五年)は香織の辞退という形で、その無垢を保ったまま終わってしまうので、リズを見ることでその構図を見出すことができるようになる、といった方が正確かもしれない。公式サイトのスタッフコメントにあるような、「欲望は空へ羽ばたく翼にもなりますが、自分や誰かを閉じ込める鳥かごにもなります」というテーマは、『響け! ユーフォニアム』シリーズにかなり初期の段階から内在していたものであると言えるだろう。
やや本題から逸れてしまったが、このことは「欲望は常に正当性を担保する建前としての大義名分を必要としており、そうした体面を、体裁を保てなくなれば、その正当性は消え去り、欲望自体が罪悪感となって失われてしまう」というようにまとめておこう。このように考えれば、希美の視点での「愛ゆえの決断」がはじめから存在したことと、希美がその実現にショックを受けることとの間の矛盾を解消することができるだろう。
さて、随分と遠回りながら、これで「希美のメッセージがみぞれに届くまでの物語」として『リズと青い鳥』を形式づけることを主張できるようになった。では次に、そのストーリーの中で、みぞれはいかにして希美のメッセージを受け取るようになったのかを考えたい。出発点からはじめよう。どうしてみぞれは、希美の「頑張ろう」という言葉を文字通りに受け取らず、その裏を読み取ったのだろうか。
まず取り上げたいのは、みぞれの「本番なんて一生来なくていい」という台詞だ。これは希美が「本番、楽しみだね」というのを受けてのものになるが、なぜみぞれはそう思わないのだろう。
このことはもちろんというべきか、希美との別離に関連づけられるべきだろう。「希美と一緒にいたいから、オーボエも頑張った」というように、彼女にとっての楽器や演奏、吹奏楽部とは、希美との絆を保証するための手段としての価値を持っていることがわかる。逆に言えば、それがなくなれば2人の縁を繋ぐものは消えてしまうと考えているのだろう。直接的な言及はないが、彼女が童話『リズと青い鳥』にあれほどまでに心を揺らされたのは、卒業というタイムリミットへの意識がもとからあったことによると考えられる。希美が音大の受験を決めたときにみぞれが色めき立ったのは、それが自分も惹かれていた進路だったから、などということでは恐らくない。単に希美の進路を知ることができたからだろう。
この卒業と進学に対する意識については、優子と夏紀の関係との対比によって描かれている。希美が音大の受験を決めたあと(=みぞれが音大の受験を決めたあと)のシーンでの2人のやり取りは、まとめるならば自分と同じ志望校を選んだ優子を夏紀がからかい、優子はあくまで偶然だと主張するというものだ。対して、同様に希美と同じ進路を選んだみぞれは「偶然」ではなく「希美が受けるから」という。ここでは優子が実は夏紀と同じ大学に行きたかったのか、はたまた本当に偶然だったのかはわからない。だが重要なのは、それがわからなくても互いにとって問題がないということだろう。この2人の間には、別に同じ進路を望んでいなくても、あるいは実際に進む進路が別々であっても、それでも関係は続いていくという信頼関係が互いに存在しているということが、ここで描写されているのだ。
翻って、希美とみぞれの間にはそれがない。いや、希美にしてみれば、みぞれがどこまでも自分についてくるであろうことは信頼できるだろうが、みぞれにとっての希美とは、「今度いついなくなるかわからない」という言葉に表れているように、絶対的な不信と不安の対象となっている。
そしてこの台詞が登場するのは、ちょうどみぞれの「希美の決めたことが私の決めたこと」や、麗奈の「希美先輩が自分に合わせてくれると思ってない」という台詞と同じシーンである。となれば、この3つの台詞から、作中に通底するみぞれの基本的なスタンスのようなものを考えることができるだろう。希美は自分に合わせてくれなくて、今度いついなくなるかわからないから、希美の決めたことに合わせる必要があるのだ。
では、こうした関係の非対称はなにを端緒として生まれているのだろうか。このことについては回想に描かれた前日譚、希美の退部の一件を考えるべきだろう。みぞれの演奏のシーンでは、絵の具で描かれた青い鳥が飛ぶカットが挟まれているが、同じ絵はみぞれが希美の退部を知るシーンの回想でも使われている。このことから、本編での希美と同じ立場にみぞれが置かれていることを読み取ることは難しくないだろう。ここでは、冒頭でもみぞれが口癖のように繰り返している「知らない」という台詞が強調されていることを取り上げたい。
当たり前のようだが、この台詞には単に希美が部を辞めていたことを知らなかったという以上の意味が込められている。あえて書き出すならば、「私は友達なのだから希美からそのことを知らされているべきだったのに知らなかった」とでもなるだろうか。もちろん、ここで希美の行動が意味していたのは、みぞれのことを友達だと思っていなかったということではなく、みぞれに退部を知らせるべきだとは思っていなかったということだろう。ここで描かれているのは、希美にとってなんでもないことがみぞれにとっては特別であるというすれ違いが最初に自覚されたシーンであるとも言えるかも知れない。公式サイトの原作者のコメントにあるように、「自分の好きな人が自分だけを見てくれるとは限らないし、自分と相手の好きの重さが全然釣り合ってなかったりする。」というわけだ。
「知らない」という台詞でこの回想と冒頭とが結び付けられていることから、映画の始まりで希美が『リズと青い鳥』に自分たちを重ねたような構図が、比喩としてではなく作中の現実として決定づけられたのがこのタイミングであり、後にみぞれが希美の「愛ゆえの決断」を信頼することによって、リズの役を希美に移したように、最初にみぞれがリズの役を負うことになったのがこのシーンであると解釈することもできる。ここで回想されているのは『リズと青い鳥』の幕開けのシーンである、と言い換えてもいいだろう。
要約すれば、ストーリーの前半部では、みぞれにとってコンクールは希美との別離へのタイムリミットであり、モチベーションがないどころか積極的に忌避されるものであるということだ。みぞれの手加減がいつから、どのような思いで行われていたのか、映画内では描写されていないが、そこには希美に合わせるという積極的動機とコンクールに興味がないという消極的動機が混在していたと考えられる。体育の授業のシーンでは、やるべきことを無視してはばからないみぞれのふてぶてしさというものが説明されているのだろう。コンクールなんてどうでもいいばかりか、それが終わってしまえば希美との縁が切れてしまうかも知れないのだから、やる気なんて出るはずもないし、それで希美が楽しく部に居続けてくれるなら手を抜くことを躊躇う理由もないというわけだ
物語の出発点の座標を確認したところで、次はその推移について考えよう。みぞれはどのようにして希美のメッセージを受け取ることができるようになったのだろうか。
この転換点は、主要登場人物を順に挙げていけば誰もが3番目に思い浮かべるであろう、剣崎梨々花に求められるように思う。彼女がみぞれに接近するシーンは四回登場する。一度目は冒頭のダブルリードの会への誘いを断られたとき。ここでは希美とフルートパートが打ち解けていることとの対比がされている。二度目もまたダブルリードの会への誘いを断られたとき。「のぞ先輩」呼びを意識して「みぞ先輩」と呼ぶようになることから、ここでもフルートパートとの対照を見て取ることができる。付け加えるならば、剣崎後輩がみぞれに望んでいる関係とは、希美とフルートパートの関係と同じようなものであるということが表現されているのだろう。三度目はオーディションに落ちた後。この後に、希美の誘いにみぞれが「他の子も誘っていい?」と返し、希美が動揺する様が描写されている。最後の四度目はその後、ふたりで一緒に練習曲を吹いているシーンである。このあとの合奏のシーンと、みぞれへの高坂後輩の糾弾を皮切りに、希美との間の不調和の描写があからさまになっていく。
梨々花がみぞれに望んでいたものが、希美とフルートパートとの関係と同じようなそれであると解釈するならば、つまり彼女は単に個人的な好意としてだけでなく、優子の言葉に象徴されるような、吹奏楽部の部員としての連帯をみぞれに求めているということが示されているのだろう。ここで重要なのは、三度目のときの「先輩と一緒にコンクール出たかったです」という台詞だ。この言葉は、こうした梨々花の願望が端的に表れたものであると考えられる。そして、梨々花のこの言葉にみぞれが心を動かされたことの意味は、梨々花から向けられる好意を無視できなくなったことと、それによってコンクールというものがみぞれにとっても実際的な意味を持つようになったことの2つにまとめられるように思う。
このことは、みぞれの手加減における希美に合わせるという積極的動機とコンクールに興味がないという消極的動機に対応していると言えるだろう。彼女が希美に合わせることができなくなり、終幕へのトリガーが引かれたのがこのシーンであると考えられる。これに関しては特に作劇上の必然性やロジックといったものは抜きに、単にさしものみぞれも目の前で泣きじゃくられては同情心が働いたということなのだろう。逆に、もしみぞれがここでなにも思わないほど希美に心酔していたなら、少なくとも高校生のうちは2人の関係は同じまま、順調に歪みを溜めていっただろうことは想像に難くない(この場合、希美がみぞれの実力を知るとすれば、それは受験の失敗と高校最後のコンクールをふいにしたこととして表れることになるだろう)。さらに言えば、もし希美の退部の段階で打ちひしがれて諦められる程度の好意だったなら、そもそも問題自体が存在しなかっただろう。思いの重さの差が、そのまま問題の大きさと直結していることがわかる一幕である。
このシーンの後から表出する希美とみぞれとの不和は、夏紀とのやり取りの中で希美自身の口からも説明されている。時系列としては、みぞれと梨々花の四度目のシーン、息の合わない合奏、優子とみぞれの会話(と麗奈の乱入)に続く場面である。特筆したいのは、みぞれに対して「よそよそしくない?」「ソロのところも、なんか息あわないし」と希美がこぼすごとに、みぞれとダブルリードの面々が交流するカットが挟まれることだ(考えてみたらこれを5度目にカウントするべきだったかもしれない)。こうした演出は、みぞれと希美、みぞれと梨々花たちという2つの関係の間の対立を印象づけるためのものだろう。希美に合わせて手加減をすることと、部の一員としてコンクールのために努力することは両立しない。「合わせる」ことと「支えあう」ことの対比、とでも言うべきだろうか。
ここで梨々花が望んでいた関係は希美とフルートパートの関係と同じであるということを踏まえると、さらに読み取れるものがある。というのも、みぞれと希美の一度目のやり取りの前、そして「のぞ先輩」呼びが初めて登場した場面で、「きみら、そんな可愛い重要?」という問いに一斉に「重要ですよ」と答えたメンバーたちに、希美が「息あってるね」と応じる場面があるからだ。希美とフルートパートは息が合う、みぞれとダブルリードは息が合う、しかし希美とみぞれは息が合わない……。このことから、この「可愛い」という要素こそ、「息を合わせる」ために重要なのではないだろうか、ということが考えられる。
このフルートパートのやり取りが前にも引用した優子部長の宣言に続くものであるということは恐らく意味のないことではない。優子の言葉とフルートパートの雑談は、ちょうど『響け! ユーフォニアム』の考察で述べた外向きの体面と私的な欲望として並列させることができないだろうか。そして香織がなぜそうした建前を抜きにした内心のレベルで成功を望まれるのかといえば、それは香織が「可愛い」からではないだろうか。
このことから、「可愛い」とはなにかという抽象的かつ大仰な問題を考えざるを得ない。ここで参照したいのは、第一に『囮物語』の千石撫子である。
まず、千石撫子の可愛さが、先に考察した香織や希美、あるいは神原が持つ性質といかに相同しているかという点を確認したい。この点については、忍野忍の優れて批評的な台詞がある。
「黙っているだけでみんなが親切にしてくれたりはせんのか? 黙っておるだけで頭がいいと思われたりはせんのか? 黙っておるだけで思慮深いと思われたりはせんのか? できなくても笑ってもらえんのか? 静かにしておるだけで、嫌なことをやり過ごせるのではないか? 人とおなじことをするだけで、人より高く評価されたりはせんのか? 同じことを言っても、人より感心されたりはせんか? 失敗しても、怒られたりせんのではないのか? 嘘をついても、許してもらえるのではないか?」「困っていると」「誰かが勝手に助けてくれたりは、せんのかのう――揉めていたら、勝手に被害者だと思ってくれたりの」
西尾維新(2011)『囮物語』講談社.P148-149
……まあ、なんというか、これ以上なにを言えばいいのやらという感じだが。忍の舌鋒は「うぬは怪異よりも、よっぽど妖怪じみておるという話じゃよ」と結ばれている。これは忍野メメが怪異に関わった人間に対して「被害者面が気に食わねえっつってんだよ」と言い放つのと並べて読むことができるだろう。同様に、「誤解を解く努力をしないというのは、嘘をついているのと同じなんだよ」という言葉も、この可愛さへの批判として解釈することができる。「好きで可愛いわけじゃない」という撫子に、阿良々木月火は「『可愛い』だけで贔屓されたり褒められたりするのが嫌なんだったら、『可愛い』以外のところを伸ばせばいいだけじゃない。努力して、頑張って」というが、ここで「努力」という言葉が用いられていることも、その傍証となるだろう。
特に臥煙伊豆湖の台詞にはひとつの重要な手がかりが含まれている。「可愛い」と「誤解」の関係である。努力にまつわる2つの警句を並べてみると、誤解されることと可愛いこととの相同性を見て取ることができるだろう。素朴な感覚に沿って言い換えるならば、可愛いというのは本人が思っている以上に可愛いということなのだ、というように言えると思う。例えば、もし香織にそれを優子が見つけることを期待して譜面を開いておくようなような計算高さがあったなら、この上なく興ざめではないだろうか。香織のメッセージは、本人がそれを伝えていないからこそ伝わるのである。
とにかく、ここで確認しておきたいのは、「可愛い」という言葉が、『響け! ユーフォニアム』のエピソードを検討したときにを体面や建前、大義名分と呼んだものと深くかかわっているということである。可愛さの定義として、ここではいったん「わかっているが、それでも……」という言外のメッセージを発する能力、あるいは誤解をさせる力とまとめておきたい。これは滝先生が「音楽には、楽譜に書ききれない間合いがあります」という台詞を踏まえれば演奏にも当てはめることができるだろう。「息があう」とは、つまりそうした口にされないルール、暗黙の了解を共有することなのだ。「言外の意図」を内心や心中といったものと同一視するならば、あるいは「好きの重さが釣り合う」状態として想定されているのも、そういったものの共有なのかもしれない。
ここで改めてリズの内容に戻ろう。希美とフルートパートは息が合う、みぞれとダブルリードは息が合う、しかし希美とみぞれは息が合わない。この関係を整理すれば、希美もみぞれも吹奏楽部との連帯を成立させていながら、希美とみぞれとでは反目しあう、友達の友達は敵という構図を描くことができる。このことが先に確認したみぞれのコンクールに対する意識の変化によるものであることはいうまでもないだろう。物語が「みぞれと梨々花の仲が深まるほど、希美とは息があわなくなる」という推移を描いていることは、直感的にもたやすく見て取ることができる。
では、ストーリーのそうした流れにはどのような必然性があるのだろうか。このことは、希美がどちらがより上手いかという部分を重視していることに求められるように思う。「希美は、練習が好き?」「好きだよ。めっちゃ好き」と「本番、楽しみだね」という台詞を前にも取り上げたが、こうした台詞が吹奏楽部に対する強い連帯意識を表していることを再度確認しておきたい。希美の部に対する愛着は、集団の理念を擬人化して考えるとわかりやすいだろう。ここでももう一度「するがモンキー」を参照したい。希美を神原に、みぞれを阿良々木に、戦場ヶ原を吹奏楽部にそれぞれなぞらえて考えると、希美とみぞれの対立が見通しやすくならないだろうか。2人はある意味で、どちらがより吹部にとって価値を持つかを競う恋敵なのである。加えて、阿良々木とみぞれの立場の相似性として、本人は相手を敵としては認識していないというものがある。「僕は、お前なんか、嫌いじゃないんだ」と言う阿良々木と、「希美のフルートが好き」とは言わないみぞれは、相手にとってなによりも大切なものを大切にしていない、「好きの重さが釣り合っていない」という点で共通の立場にいるといえないだろうか。貝木泥舟が「好きな奴がお前のことを好きになってくれるとは限らないのと同様 ー嫌いな奴がお前のことを嫌いになってくれるとは限らないんだよ。そして嫌われてくれるとさえ限らないんだ」というのは、こうした構図を実によく説明している。
勝利の価値を踏み乱し、敗北の負債を踏み倒し、開き直って勝負を放棄すること自体が、その勝敗にこだわる人間への最大の打撃となりうる。話はそれるが、球磨川禊と戯言遣いの相同性はこうした攻撃性を用いているという点にあるのだろう。『めだかボックス』(二〇一〇年)の球磨川事件編が手元にないので『戯言』シリーズ(二〇〇二年)のみを参照することになるが、園山赤音に対して、貴宮むいみに対して、紫木一姫に対して、春日井春日に対して、彼は「殺さば殺せ」といわんばかりの態度を崩さない。これは対レイニーデビル、対障り猫における阿良々木暦の基本姿勢でもあるといえるだろう。
そして、いーちゃんも阿良々木暦も、物語を通して最終的にはそうした勝負の内側へと踏み込んでいくことになる。ここでその変遷を論じるには準備と余裕が足りないが、もうひとつ重要なことは、彼らにはこうした勝負からドロップアウトするきっかけとなった、原体験やトラウマと呼べるエピソードが存在するということである。戯言シリーズでは最後まで秘されたままだが、<物語>シリーズでは『傷物語』(二〇〇八年)がそれに相当するだろう。であれば、「するがモンキー」での神原の立場に、「こよみヴァンプ」の阿良々木を重ねることができるはずだ。
ここまでの「するがモンキー」の考察を踏まえるならば、その相同性がもっとも顕著なのはやはり最終盤、阿良々木がキスショットが自ら進んで殺されようとしていることを知るシーンだろう。キスショットには悪意こそないが、このことには戯言遣いや球磨川禊と同じ攻撃性が宿っている。この構図はキスショットに首を差し出す阿良々木にも、阿良々木に食べられてもいいという羽川にも見て取ることができるだろう。いーちゃんの自虐や露悪趣味は、こうした自己犠牲が相手を最大限に貶めるための手段であるということに対する自覚に根ざしたものとして解釈することができるかもしれない。「自分が死ぬのはいいけれどー人が死ぬのは気分が悪い。考えてみれば、「勝手な意見だ」というのは、かなり『傷物語』の核心を突いた反省であるといえるだろう。専門家の忍野メメが「人はひとりで勝手に助かるだけ」という点にこだわることも、こうした人助けが化物じみたものであるということを示しているように思う。
こうした、食べる、食べられる、食べさせる、食べさせられるという形の関係は、『リズと青い鳥』の読解にも繋げることができる。それも本編ではなく、童話の『リズと青い鳥』である。食べられることと食べさせることとの違いは、忍野メメの「きみが吸血鬼の人喰いに嫌悪を憶えたのは、言ってみれば可愛らしい猫ちゃんが鼠を食べているシーンを見て幻滅するのと同じだよ。そしてきみは、言わばペットとして吸血鬼を飼うことを選んだんだ」という言葉に表れているように思う。自身を食べさせるということは、相手を家畜として飼うことでもあるのだ。『傷物語』の登場人物たちの、一見すると美し自己犠牲の輪は、そのまま相手に対する支配権をめぐる戦争でもあるといえる。「フグに餌あげてた」というみぞれに、希美が「リズみたい」と返すのは、「食べさせる」という行為がリズをリズたらしめていることを示しているのだろう。自己犠牲と飼うことの関係は、「希美の決めたことが、私の決めたこと」という台詞と前後して、「私がリズなら、青い鳥をずっと閉じ込めておく」とみぞれが言っていることにも表れているといえるかもしれない。
また、「はまってるの? フグ」「うん、可愛い」という会話から、可愛いことと飼われることの関係を考えることもできる。例えば、香織はその可愛さのために、自身のメッセージとは裏腹に、その意志を「諦めたくない」と誤解されたわけだが、その意志に従うことには、まさに戯言遣いのような残酷さがないだろうか。これは希美にスライドして考えるとさらにわかりやすい。みぞれの本気を前にした希美の寄る辺なさとは、自分が努力して掴み取ったと思い込んでいた「みぞれと同等」の立場が、みぞれから給餌されたものに過ぎなかったということに根ざしているといえないだろうか。この構図はキスショットが死ぬつもりだったことを知った『傷物語』の阿良々木にもそのまま当てはまるだろう。
結局 ー僕が望みを叶えただけじゃないか。
誰も幸せになっていない。
キスショットに全てを押し付けているだけだ。
これは羽川からキスショットの真意を告げられたあとの阿良々木のモノローグだが、ここで「誰も幸せになっていない」という言葉が使われていることは見逃せない。なぜなら『傷物語』は冒頭でも述べられているように「バッドエンド」、「みんなが不幸になることで終わる」物語だからだ。よって、ここでは「望みを叶える」ことと「幸せになる」ことの区別を考える必要がある。これは『響け! ユーフォニアム』を考察したときの建前と本音の関係、自身の満足は他者の利益ためという建前のもとでしか得られないというジレンマを確認すれば十分だろう。単に望みを叶えるだけでなく、大義名分のもとに望みを叶えなければ幸せにはなれないのだ。誰かに飼われるままに望みを叶えても、幸せになることはできない。『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(一九六八年)ではないが、人はとにかくなにかを飼っていなければならないのである。「みんなが幸せになる方法を教えてほしい」という阿良々木に、「あるわけないじゃん、そんなの」と返す忍野の言葉は、こうした自己犠牲がもたらす幸せと、それによって望みを叶えられる不幸を念頭に置くことで理解することができるだろう。
このように『リズと青い鳥』と『傷物語』の間に相似を見るならば、みぞれの立場にはキスショットが当てはまることになるだろう。この2人の立場が交わる点として、どちらにとっても物語は「ひとりぼっち」でいたところを救われるところから始まるというものがある。このときに、キスショットが「儂はうぬのために死のうと」決めたのと同じような思いがみぞれにも生まれるわけだが、その後の展開の対称性にも興味深いものがある。彼女たちはどちらも、「青い鳥」に逃げられることになるのだ。
人を喰ったために阿良々木に拒絶されるキスショットと、あくまでその好意が希美に届かなかっただけで当人に非があるわけではないみぞれとでは、その印象には天と地ほどの隔たりがあるかもしれない。だが、みぞれと希美の関係が端的に要約された「好きの重さが全然釣り合ってなかったりする」という一文を思い起こせば、ここで起こっているすれ違いを同一視することは難しくないだろう。「通じ合ったつもりになっていても。こっちが勝手に絆を感じていても。所詮――食べ物なのである。」という文章は実に示唆的である。言葉は通じても心は通わない。この非対称は、キスショットが頭を撫でるように要求したシーンに、「吸血鬼は違うルールで動いているようだった」というモノローグが挟まる段階ですでに表れているといえるだろう。『リズと青い鳥』の悲劇とは、究極のところ希美のルールとみぞれのルールの食い違いという点にまとめられるように思う。そしてこのルールとは説明できるものとしてはっきりと理解されているようなものではなく、言うまでもなく、暗黙の了解として存在するものである。だから実際にそれが破られるまで、相手にそのルールが通じているかはわからないのだ。言うまでもなく人は食糧だと思っていたというのがキスショットの立場なら、過去のみぞれは、言うまでもなく自分は希美にとっての特別だと思っていたのだろう。阿良々木がキスショットの頭を撫でたとき、本人がどんなつもりであれ、それは吸血鬼の文化を受け入れ、人喰いを認めたということになるのだ。このことについては、阿良々木自身も「お前のために死のうと、僕は思ったんだからな ーそれはつまり、お前が人を喰うことを許容したってことだ」と言及している。ごちゃごちゃと並べてきたが、要はアンジャッシュ状態という言葉を使えば誰もが一発で頭に思い浮かべられるシチュエーションが、『傷物語』にも『リズと青い鳥』にも発生しているということである。
このように考えると、最後に阿良々木がキスショットの頭を撫でるシーンの感動的なまでの残酷さというものがわかるだろう。「頭を撫でるのは、服従の証」というが、ここで阿良々木はなにに服従しているのだろう。キスショットの「死にたい」と「死にたくない」は、ちょうど香織の「諦める」「諦めたくない」に相当しないだろうか。繰り返すように、ここで本音を採用し、願いの裏を読むような自己犠牲は、相手を家畜に貶めてしまう。キスショットは誤解を解くことに失敗し、ずっと弱ったまま、可愛いままの存在に成り下がってしまうのである。阿良々木が従僕となることで人喰いを認めてしまったように、キスショットは主となることで「死にたくない」ということを認めてしまったのだ。頭を撫でる行為の反復は、この致命的な非対称を象徴しているように思われる。誰もが誰かのために生きて死のうと願った結果、全員で無意味に生き残ってしまう。『傷物語』のバッドエンドの輪郭は、概ねこのように描写されるだろう。
さて、話が『リズと青い鳥』からずいぶんとそれてしまったが、ここでもう一度、希美が「きみら、そんな可愛い重要?」といった場面に立ち戻りたい。可愛さと誤解の関係を踏まえれば、一斉に「重要ですよ」と答えた部員たちからハッピーアイスクリームと同じモチーフを見出すことは難しくないだろう。それ自体にはなんの意味もない「ハッピーアイスクリーム」という言葉から、同じ意味を「誤解」することーこれはまさに暗黙の了解が共有されたシチュエーションの格好の例であるといえる。このことは劇中に登場するもうひとつ独特なミームにも当てはめて考えることができるだろう。本作のキーワードは「大好きのハグ」である。
ハッピーアイスクリームと大好きなハグにどこか似たところがあるというのは、直感的にもなんとなく感じとることができるかもしれない。そうとでも解釈しないとハッピーアイスクリームの挿話が本当に意味不明になってしまうというメタ読みもその傍証とできるだろう。しかし、このことはここまで論じてきた建前と誤解の関係を用いてきちんと説明することができる。香織に対する優子の立場を考えればわかりやすいだろう。先にも少し触れたが、優子はいくら香織が好きだからといって、また事実としてそうであるからといって、「麗奈の方が上手いけど、そんなこととは関係なく香織先輩が好きです」とは言えないのである。これはちょうど、レイニーデビルが戦場ヶ原を攻撃できないのと似ているだろう。レイニーデビルが神原のために暴力を振るうならば、戦場ヶ原先輩のためという神原の建前を犯すわけにはいかないように、優子もまた、香織が吹奏楽部の目標ために無私の働きを見せているという見せかけを汚すわけにはいかないのだ。表あっての裏 ー願う側に言い訳が必要なら、叶える側もそれに適った叶え方をしなければならないのである。
そして「大好きのハグ」は、吹部の目標と同じように好意(神原の場合は悪意だが)を表明するための建前、言い訳であるといえるだろう。これは大好きのハグで表明された好意は単なる建前で、意味のない冗談であるというのではない。むしろ逆で、これは意味のない冗談で、単なる建前である、という建前を共有することによって、「誤解」として本音を伝えることを可能にするためのものなのだ。これはちょうど、香織のメッセージの裏側を吹奏楽部全体が共有していたことに通じるだろう。こうした構図を逆方向から描いたものとして、音大の受験に関して「希美が受けるから、私も」というみぞれの言葉を、希美が「なに本気にしてるの、ふたりとも。みぞれのジョークじゃん」と流すシーンを見ることもできる。「好きの重さが釣り合う」状態を、こうした暗黙の了解を共有することとして考察したが、「大好きのハグ」が冗談めかして重みを取り払うことによってその釣り合いを実現するのとは裏腹に、真剣に口にされたものはそれ自体を冗談として処理することで釣り合いを取っていると考えることもできるだろう。
みぞれが大好きのハグを見てるだけでやったことがないということから、こうしたミームと「ひとりぼっち」であることの関係を考えることもできるだろう。同じメッセージを同じ意味に「誤解」すること、つまり暗黙の了解を共有することこそが、「息を合わせる」ことの条件なのだ。忍野メメが重し蟹を踏みつけながら「言葉が通じないなら戦争しかない」と言うのは、阿良々木とキスショットの頭を撫でることをめぐるすれ違いとそれに続く決闘のように、メッセージの解釈をめぐる問題として位置づけられるだろう。これは香織のメッセージを文字通りに解釈しようとした麗奈が「悪者」になることにも同じことが言える。これらの物語は総じて、言葉が通じない相手との共存を巡るものであるということもできるかもしれない。
このことから、理科室での大好きのハグは、みぞれが徐々に他の部員たちと打ち解けていったことを念頭に置いて考える必要があるだろう。みぞれが吹部への連帯意識を持つようになる流れに関しては先にもまとめたが、この文脈から付け加えたいのは、そうしたみぞれの立場の変化が、実力を発揮することだけでなく、希美に自身の想いを伝えることにも関わっているということである。みぞれの本気を引き出したのが麗奈の「先輩の本気の音が聴きたいんです」という言葉に象徴される部の共通の目標への意識なら、みぞれの本心を引き出したのは「大好きのハグ」という共通言語であるといえるだろう。香織と優子の関係を考えるときに触れたように、実力という建前を抜きに好意を表現することはできない。そこでみぞれが採用したのが、「大好きのハグ」という別の建前であると考えることもできる。これは「今度オーディションがあるけど、選ばれたメンバーもそうでないメンバーも、チームの一員であることは変わらないから、みんなで支えあって最強の北宇治を作っていこう」というメッセージを、実際のレベルで実行したものであると解釈することもできるだろう。優子が香織に対する好意を表現するときに用いた建前が「実力」なら、みぞれの大好きのハグは、「チームの一員」であることに支えられた好意である。先の考察では、みぞれと希美、みぞれと梨々花たちという2つの関係の間の対立から「合わせる」ことと「支えあう」ことの対比を見たが、「支えあう」ことを選ぶことは必ずしも希美を切り捨てることではない。こうしたメッセージが優子から発されていることは、この物語にひとつの感動的な倍音を添えているといえるだろう。
さて、このみぞれの決断への最後の後押しとなったのは、言うまでもなく新山先生とのやり取りである。希美か、吹部か、という板挟みの中で葛藤するみぞれは、希美もまた部員であり、「チームの一員」であるというごく単純な事実を見落としている。『響け! ユーフォニアム』を考察したとき、私的な欲望に対する合目的性と公的な目標に対する合目的性とを区別したが、この段階に至るまで、みぞれには希美の個人的な満足以外は考慮の外だったのだろう。新山先生の「あなたが青い鳥だったら?」という言葉は、作中の現実に当てはめるならば、この「希美も部員である」という事実を指摘するものとして読むことができるはずだ。
『リズと青い鳥』の配役の交換は、『傷物語』を参照して考察した飼う/飼われるの定義を踏まえるならば、みぞれは希美を飼うことを諦められた、というようにまとめられるだろう。「希美の決めたことが、私の決めたこと」というようなみぞれの強迫的な献身は、本人も言うように「青い鳥をずっと閉じ込めておく」ためのものであり、希美を飼い殺すための努力であることがわかる。では、彼女が最終的に自身が希美に飼われる立場となることを受け入れることができたのはなぜか。このことは『傷物語』の阿良々木に当てはめれば、キスショットの本心を知りながらキスショットを喰い殺すこと、「死にたい」キスショットの表の願いを叶えることにあたるだろう。結局、阿良々木は自分のためだけにキスショットを殺すことができなかったわけだが、ではどうしてみぞれにはそれができたのだろうか。その根拠は、みぞれが全力を出すことが梨々花や麗奈のためにもなるということに求められるだろう。人はとにかくなにかを飼っていなければならない ーみぞれには吹奏楽部という新しいペットがいたからこそ、希美を飼うことを諦められたのである。こうした集団の理念と個人への執着が代替的なものであることは、「するがモンキー」の戦場ヶ原ひたぎを例にとって論じた通りである。みぞれは希美との関係において青い鳥になると同時に、吹部との関係においてリズの立場を占めるようになったと言い換えてもいいだろう。
このことから逆算すると、ストーリーの前半部では、みぞれ自身が吹奏楽部にとっての青い鳥だったということも言えるだろう。可愛いことと飼われることの関係についてはすでに論じたが、忍野忍が列挙した「可愛い」の特徴は、かなりみぞれにも当てはまっていないだろうか。「黙っているだけでみんなが親切にしてくれたりはせんのか?」とか、「静かにしておるだけで、嫌なことをやり過ごせるのではないか?」とか。体育の授業での夏紀の描写に顕著だが、みぞれに対してそうした世話を焼くことにけっこうみんな乗り気っぽいところも、この『リズと青い鳥』の構図を裏付けているように思う。
みぞれの視点から見たストーリーの流れは、ここで冒頭の考察に繋がることになる。観客がみぞれを青い鳥の立場に重ねるタイミングはその演奏技術が明らかになるシーンを待たなければならないが、新山先生がみぞれを青い鳥になぞらえるときにその根拠とするのがみぞれの技術であるはずはない――それは互いに自明のことだからだ。みぞれは自分の能力に指摘されて気づくような「なろう系」に分類される人物ではない。よって、新山先生がみぞれを青い鳥の立場に置くことで気づかせたこととは、希美もまた梨々花や麗奈と同じように、みぞれの「本気の音」を望んでいるということだろう。物語の語り手として、カメラのようにひたすら希美を見つめ続けたみぞれが、他者からのまなざしを受けとるようになる――最初に確認したみぞれから希美への視点の移動は、こうした物語の流れを演出の面で表現したものであるとも言えるだろう。
以上の考察を踏まえるならば、本作のハッピーエンド、山田尚子監督のインタビューにあるような「大きさの違う歯車同士がある一瞬動きが重なる」タイミングは、みぞれが譜面に「はばたけ!」という書き込みを見つけるシーンに求められるべきだろう。『響け! ユーフォニアム』を参照したとき、香織の「ソロオーディション/絶対吹く!」という書き込みをコミュニケーションのボトルネックとして取り上げたが、希美のメッセージがこれとちょうど反対の内容であることは恐らく偶然ではない。まさに譜面の余白において、希美がみぞれを求め、みぞれがそれに応える。互いの心中が通い合うこの一瞬の崇高さは、この映画を見たことがあれば誰もが感じ取ったことだろう。
さて、これで本作の主だった内容は概ね回収し終わったように思う。最後になるが、この映画の内容以外の部分、メタフィクションとしての本作がどのように観客と関わっているかについて考察して、この文章を締めたいと思う。いよいよ与太中の与太、余談中の余談になってしまうが、冒頭で述べた「私はさっきまでみぞれだったのに、いつの間にか希美になっていた」という感覚は、<物語>シリーズの怪異について考える上でも少なからず重要な意義を持つように思われるからだ。
怪異たちに共通する性質として、本文では「願いを叶える」という点を取り上げたが、ここに着目するならば、もうひとつ共通点となる要素を見つけることができる。願いを叶える代償として、怪異が取り立てていくものだ。『化物語』から作中でも例外とされている蝸牛と蛇を除外した鬼、蟹、猿、猫には、どれも身体を乗っ取るという点が共通している。不死身の身体、奪われた体重、猿の手、猫耳、といった具合だ。
こうした願いを叶えることと身体を奪うことの関係は、西尾維新の別作品にも見ることができる。『きみとぼくの壊れた世界』では、主人公が小学生のとき、いじめられている妹を助けたエピソードが回想されている。いじめの存在にに気づいた主人公――櫃内様刻という――は、妹――夜月という――の足を折って入院させ、腹を殴って加害者の名前を吐かせ、カモフラージュ用に無関係の生徒数人を巻き込んで制裁を下すのだ。このことが極めて化物じみていることは、ここまで本文をお読みの方ならば理解できるだろう。事実、神原が最初に猿の手に願ったのはいじめの復讐だった。
そして『リズと青い鳥』で描かれた視点の移動には、これに近い気持ち悪さがないだろうか。自分の意志や行動が、思いもよらない解釈をされることによって、自身の主観が偏ったものとして、途端に信用できなくなってしまうこと ーこれには自身の身体の操縦を失うこととかなり近いものがあるように思う。ここで考察してきた阿良々木や希美、あるいは神原の立場は、『リズと青い鳥』を観ることと無関係ではないだろう。例えば、神原の願いを叶えたあと、自分の願いの裏面を、猿の手が読み取った誤解を解消するべく、それが持ち主の願いを意に沿わぬ形で叶える猿の手であるという解釈を採用した。同じように、はじめて『リズと青い鳥』を観て、みぞれの演奏にたどり着いたとき、即座にそれまでのストーリーの記憶からその伏線となる要素を拾い集め、「私にはこの事件の犯人が最初からわかっていました」と言わんばかりの理屈を脳内で組み上げなかっただろうか。少なくとも筆者はそうした。
もちろん、これは最初に断ったように、客観性のない個人の見解である。しかし、これも最初に述べたように、この映画は解釈の余地を大いに残す曖昧さを少なからず含んでいる。であれば、ひとりの個人がこの映画をどのように観たかを記録することの意義を主張することも、そこまで無理筋ではないだろう。
観測者にとってのみ意味を持つ。
観測者によって意味が違う。
観測者同士にとっての意味が一致しない。
西尾維新(2008)『傷物語』講談社. P11
これは『傷物語』の第一章で、阿良々木がキスショットを評して言ったものだが、こうした性質は『リズと青い鳥』にもそのまま当てはまるだろう。メッセージとその解釈をめぐる物語を展開しながら、その問題が作品自体としてパッケージされているという点に、この作品のメタフィクションとしての優れた点があると言えるかもしれない。すでに公開から数年が経つ映画だが、未だに汲みつくされない多義性を備えた、化物じみた傑作であるように思う。
文:大間無題



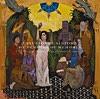

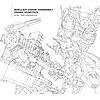



![BD 岸辺露伴は動かない [Blu-ray] BD 岸辺露伴は動かない [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/514w57s1kVL._SL500_.jpg)
![岸辺露伴は動かないⅡ ブルーレイ [Blu-ray] 岸辺露伴は動かないⅡ ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41bowAwaqJL._SL500_.jpg)
![岸辺露伴は動かないIII [Blu-ray] 岸辺露伴は動かないIII [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41+yxSPMFpL._SL500_.jpg)